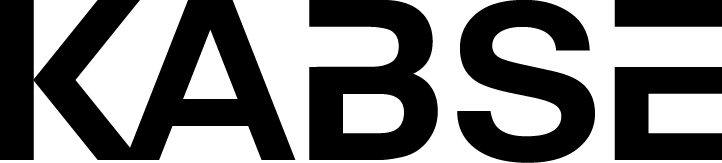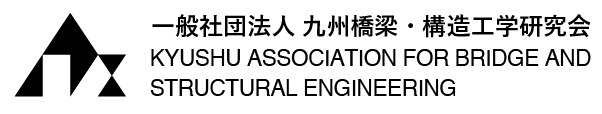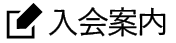主要地方道諸塚高千穂線は諸塚村と高千穂町中心部を結ぶ県道で、日常の生活道路としての利用はもとより災害時の避難路や観光振興の役割を担う重要な道路です。しかしながら当路線の椎屋谷地区はカーブが多く道路幅員も狭いため、車同士のすれ違いにも支障をきたしていました。このため宮崎県では平成24年度から丸小野橋を含む延長約1.4kmの区間において道路改良事業を進めているところです。
丸小野橋は、諸塚高千穂線において砂防河川を跨ぐ橋長47.0m、幅員8.5mの橋梁で、平成27年度から下部工に着手し平成30年4月に供用開始しました。
今回の開通により安全で快適な道路環境が確保されるとともに、利便性の向上による地域の活性化が期待されます。
※写真提供:宮崎県
橋梁概要
| 路線名 | 主要地方道 諸塚高千穂線 |
| 所在地 | 宮崎県高千穂町大字向山 |
| 橋長 | 47.0m |
| 構造形式 | PC2径間連続中空床版橋 |
| 設計荷重 | B活荷重 |
| 支間長 | 22.9m+22.9m |
所在地
※九州橋梁・構造工学研究会会報 第10号発行時(平成30年3月)の情報です。