一般県道新北九州空港線(全体)s-1024x575.jpg)
『苅田若久高架橋』は、北九州空港と東九州自動車道を結ぶ「新北九州空港線」で整備を進めている県道と町道の上を越える跨道橋です。
本橋梁を整備している一般県道「新北九州空港線」は、「北九州空港」と東九州自動車道「苅田北九州空港インターチェンジ」を連絡する唯一の路線です。ユニ・チャーム・プロダクツやトヨタ自動車九州などが立地する周辺の工業団地、また重要港湾「苅田港」へのアクセスという面でも重要な役割を果たす延長約8.0kmの幹線道路です。
「北九州空港」は平成18年に開港した九州唯一の24時間空港であり、近年、空港利用数が増加傾向にあります。また、「東九州自動車道」は平成28年に福岡県域区間が全線開通し、その交通需要は増加傾向にあります。これらを連絡する「新北九州空港線」は、主要地方道門司行橋線・町道臨空産業団地2号線と平面交差しており、交差点部の混雑解消が喫緊の課題となっていました。本橋梁の整備により円滑な通行が確保され、北九州空港、東九州自動車道間のアクセス性の向上と周辺地域の産業振興が見込まれます。
『苅田若久高架橋』は橋長は482mで下部工は14基、上部工は5つの形式に分かれた連続橋です。
交差点上に架設を行う2号橋・4号橋については地域の交通への影響が最小限となるよう夜間に全面通行止めを行い、多軸式特殊台車を用いて一括架設を行いました。その際、空港利用者等への影響が最小限となるよう各管理者との調整を行い工事の周知を徹底いたしました。
橋梁本体は令和2年11月に完成しており、令和3年春の開通に向けて橋面及び周辺の整備を進めているところです。
一般県道新北九州空港線(夜間施工写真)s-1024x690.jpg)
※写真提供:
橋梁概要
| 路線名 | 一般県道 新北九州空港線 |
| 所在地 | 福岡県京都郡苅田町~若久町 |
| 橋長 | 482.0m |
| 構造形式 | 1号橋:PC2径間連結ポステン少主桁 2号橋:鋼単純鋼床版箱桁 3号橋:PC7径間連結ポステン少主桁 4号橋:鋼単純鋼床版箱桁 5号橋:PC2径間連結ポステン少主桁 |
| 設計荷重 | B活荷重 |
| 支間長 | 34.9m+61.5m+30.0m+69.5m+34.45m |
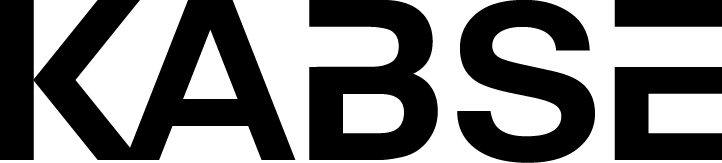
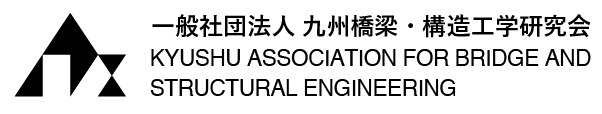

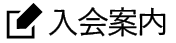







s-1024x683.jpg)












