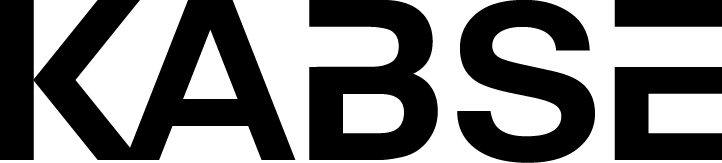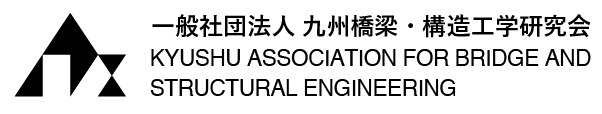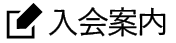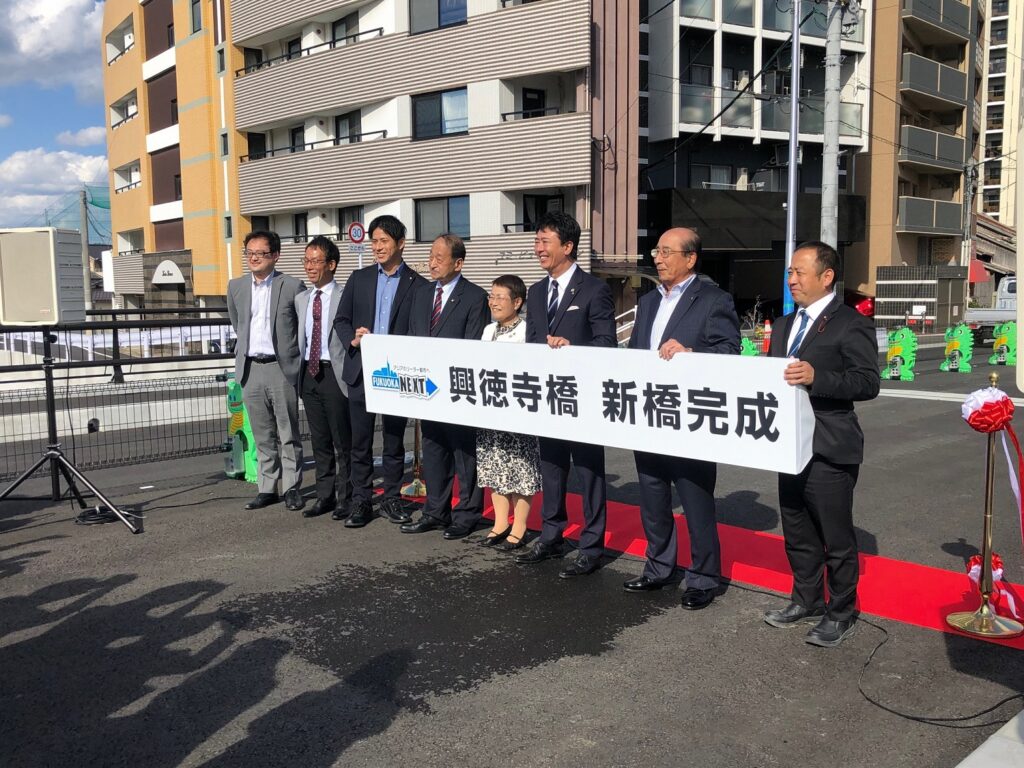下野鹿狩戸(しものかがりど)線は高千穂町大字下野から同町大字岩戸に至る一般県道であり、その沿線にある天岩戸神社の周辺では地元住民を主体とした「まちづくり」活動が活発に行われています。
天岩戸橋は歩道が無いため観光客等の歩行者と通行車両の距離が近く、歩行者の安全確保が課題となっていたことから側道橋を整備することとなりました。
本橋は地元のまちづくり等に取り組む関係者で構成された「まちづくり協議会」においてワークショップを行い、住民の意見を反映したデザインを採用しました。
主桁は逆台形断面とすることで、一般的な張出し床版を有する長方形断面に比べて点検や維持管理を容易にするとともに、鋼材重量の低減を図り経済的な設計としました。
上部工の架設方法は架橋位置が深い谷地形となることから手延式送出し工法を採用しましたが、支間長に対して施工ヤードが狭く地組できる桁の長さが制約されることから送出し作業の安全性の向上を図る必要があり、送出しジャッキと仮受けジャッキに送出し量や重量を測定する機器を取付け、重量が設計値内に収まっているか常時管理しました。また、降下設備の高さが5.0m以上となることから降下作業についても安全性の向上を図る必要があり、無線式傾斜管理システムを用いて常時降下設備の傾斜を管理しました。
本橋の整備が、天岩戸神社を訪れる観光客等の安全な通行に寄与するものと期待しています。


※写真提供:宮崎県
橋梁概要
| 路線名 | 一般県道下野鹿狩戸線 |
| 所在地 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸 |
| 橋長 | 84.0m |
| 構造形式 | 単純鋼床版箱桁 |
| 設計荷重 | 群集荷重 |
| 支間長 | 82.2m |