
NEXCO西日本が管理する関門橋は、本州と九州を繋ぐ関門自動車道の一部として重要な役割を担っています。関門橋は日本における長大吊橋の初期(1973年)に建設され、50周年の節目を迎えようとしています。
供用後30年が経過したあたりから、海上架橋や交通荷重等の影響により腐食や疲労の損傷が顕在化し始めたことで最初の大規模な補修時期を迎え、2011年から大規模な補修工事を実施しています。
補剛桁においては過去に実施した補修塗装により塗膜厚が厚く、塗膜に割れが生じていることから塗替塗装を実施しており、2022年4月に完了しました。また、床組においては長年の供用により既設線支承の回転・移動が拘束されたことで補剛材に疲労き裂が発生しており、支承取替並びに疲労き裂箇所の補修を実施しました。その他にも、主ケーブル送気システムの設置、アンカレイジ壁面の補修やハンガーロープの塗替塗装等を実施しています。
長期間にわたる補修工事では、一部の期間で片側3車線を片側1車線にする昼夜連続規制を実施しています。規制区間における安全対策を引き続き実施し、お客様への安全・安心な走行確保に尽力します。



※写真提供:西日本高速道路(株) 九州支社
橋梁概要
| 路線名 | E2A 関門自動車道 |
| 所在地 | 山口県下関市~福岡県北九州市門司区 |
| 橋長 | 1068m |
| 構造形式 | 3径間2ヒンジ補剛桁吊橋 |
| 設計荷重 | B活荷重 |
| 支間長 | 712m |
所在地
※九州橋梁・構造工学研究会会報 第14号発行時(令和5年3月)の情報です。
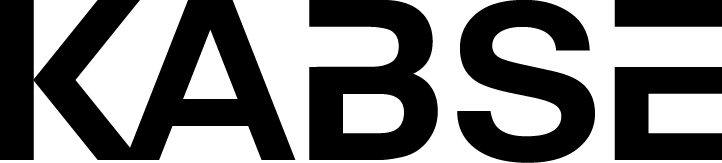
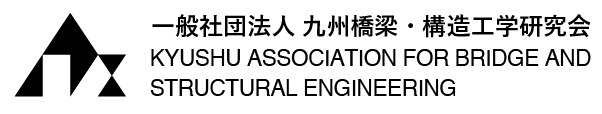

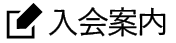






s-1024x683.jpg)









