
有明海沿岸道路は、重要港湾三池港、九州佐賀国際空港などの広域交通拠点と有明海沿岸地域の都市群を連携するとともに、一般国道208号の交通混雑の緩和および交通安全の確保を目的とする地域高規格道路で、福岡県内区間の約8割にあたる23.8kmを暫定2車線で開通しており、令和2年度の大川東IC~大野島IC間(3.7km)開通に向け工事を進めているところです。
大川東IC~大野島ICに位置する筑後川橋(仮称)は、1本のアーチリブが支点上で2本に分岐する2連のアーチ橋で日本初の橋梁形式を採用しており、九州最大の河川である筑後川を跨ぐ橋長450m、最大支間長170mの長大橋です。
本橋は筑後川の広々とした景観の中に位置し、周辺には地域のシンボルである国指定重要文化財筑後川昇開橋や土木遺産デ・レイケ導流堤などの重要文化財が存在することから、「デ・レイケ導流堤や筑後川昇開橋と共に筑後の水文化を継承する橋」をコンセプトに橋梁の色彩は筑後川の夕日に美しく染まる色彩となるよう「淡い桜色」とし、吊り材は大川市の伝統工芸である「大川組子」を表現したクロス配置を採用しています。
本橋は令和2年3月末に橋体部分の施工が完了し、開通に向けて舗装等の橋面部の施工を鋭意推進して参ります。
※写真提供:国土交通省 九州地方整備局
橋梁概要
| 路線名 | 有明海沿岸道路 |
| 所在地 | 福岡県大川市小保~大野島 |
| 橋長 | 450.0m |
| 構造形式 | 鋼4径間連続(2連)単弦中路アーチ橋 |
| 設計荷重 | B活荷重 |
| 支間長 | 最大170.0m |
所在地
※九州橋梁・構造工学研究会会報 第12号発行時(令和3年3月)の情報です
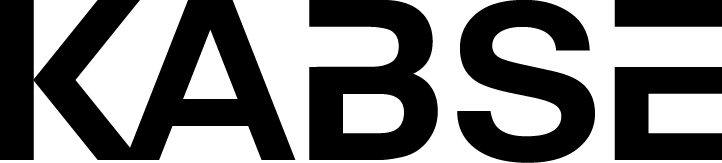
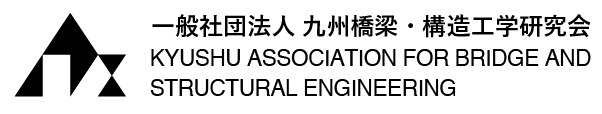

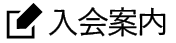















s.jpg)







