
佐賀福富道路は有明海沿岸道路の一部を構成し、並行する一般国道444号の交通渋滞及び交通隘路区間の回避を目的とした延長約10.5kmの高規格道路です。嘉瀬南ICから芦刈南ICまでの6.5km区間は平成27年度までに開通しており、六角川大橋を含む芦刈南ICから福富ICまでの3.5km区間は令和3年7月に開通しました。
六角川大橋は一級河川六角川を渡河する橋長982.0mの橋梁で、平成26年度に着手し、令和3年に完成しています。
当該橋梁の架設にあたっては分割した桁を台船で現場へ輸送し、600t吊りの起重機船を用い施工しました。その際、有明海が日本一の干満差を有し、1回当りの作業時間が約4時間という厳しい時間的制約の中での施工を行っています。
当該道路の整備により沿線地域における人・モノの交流が促進され、産業や観光の振興、災害発生時の救急・救援物資の輸送機能を強化、医療施設への救急搬送時間が短縮され、暮らしの向上に寄与することを期待しています。

※写真提供:
橋梁概要
| 路線名 | 国道444号 有明海沿岸道路(佐賀福富道路) |
| 所在地 | 佐賀県小城市芦刈町大字永田~佐賀県杵島郡白石町福富下分 |
| 橋長 | 982.0m |
| 構造形式 | (左岸側)鋼4径間連続非合成鈑桁×2 (渡河部)鋼4径間連続鋼床版箱桁 (右岸側)鋼5径間連続非合成鈑桁 |
| 設計荷重 | B活荷重 |
| 支間長 | 35.12m+35.75m+35.75m+35.25m+34.65m+35.3m +40.2m+39.225m+107.25m+190.0m+114.0m+75.225m +38.85m+40.0m+40.0m+40.0m+39.25m |
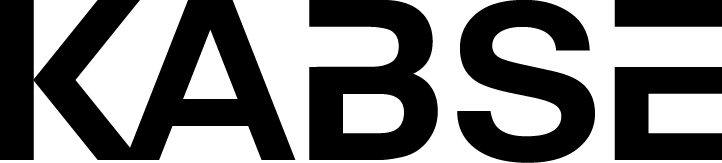
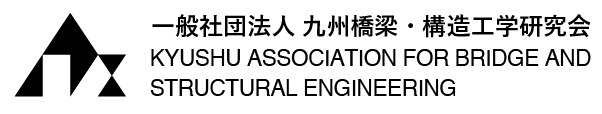

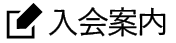






s-1024x576.jpg)

s-1024x576.jpg)
s-1024x768.jpg)

s-1024x575.jpg)
s-1024x575.jpg)




2s-1024x768.jpg)